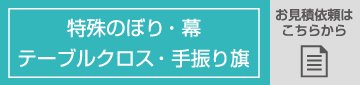小早川秀秋
防炎加工
生地変更
―武将のぼりとは―
複数の武士団が入り乱れる戦場で敵見方を区別するために掲げられたのぼり旗です。
家中によってその仕様は様々であり、武将によっては複数のデザインののぼり旗を掲げていたとも言われています。
京都のれんでは、実際に存在したと言われているデザインから、各武将の解説のより、存在したのではないか?と思われるデザインまで。様々な「武将のぼり旗」をご用意しております。
【小早川秀秋】
安土桃山時代の大名。丹波亀山城主、筑前名島城主を経て備前岡山藩主。
名は関ヶ原の戦いの後に秀詮(ひであき)と改名した。
家紋は三つ巴であるが、のぼり旗には「遠い鎌」を採用していた。
<基本仕様>
サイズ :180cm×60cm
素材 :ポリエテルポンジー
染色技法:昇華転写
縫製 :四方三巻
チチ位置:左チチ(左5つ上3つ)
1枚ずつPP入れ
小早川秀秋ののぼり旗は「鎌」の掛け合わせ
秀吉亡き後の天下統一を巡る仕切り直しの闘いは、戦国時代のような切った貼ったのやり方ではなく、味方である証拠に全国の大名から味方に付く確約書をとるなどの情報戦が威力を発揮していました。
結局その確約書が簡単に反故にされてしまう世の中なのです。豊臣家の権力は知っていながら、幼い将軍の秀頼とそのお目付役の石田三成の執政に不満を抱いていた大名はますます増えていきました。
また戦の時代へと突入するのですが、のぼり旗は敵味方を見極める大事な戦場アイテムなのです。小早川秀秋ののぼりのシンボルは「鎌」ですが、鎌は農民の農具であり、なぜ武士の命である刀にしなかったのか、そのあたりも秀秋の揺れ動く心中を察するものがあります。
「寝返った」の一言では言い尽くせない小早川秀明の心
1600年9月15日の関ヶ原の戦いは、朝8時ごろから始まり午前中は三成軍(西軍)が優勢でした。これにイライラが募った徳川家康は、再三小早川秀秋に出陣を促しますが、秀秋は松尾山城に陣取ったまま動こうとしません。
大河ドラマなどで描かれる優柔不断さが本物なのかどうかは定かではありませんが、前日まで鷹狩りなどをして遊んでいたことから推察するに、これからの時代を担っていけるのはどちらであるか、そして自分はどのような行動に出るのが正解であるかを模索していたのだと考えられます。
それだけ、一時の感情だけで衝動的に行動する単細胞大名ではなかったということです。
結局は、家康の命によりのぼりを掲げ西軍の将を攻めますが、これが連鎖反応を生みました。秀秋が東軍についた途端、それに従った同じような大名がいたのです。
時代の行方を決定づけた核心人物です。