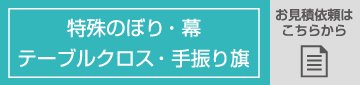豊臣秀次
防炎加工
生地変更
―武将のぼりとは―
複数の武士団が入り乱れる戦場で敵見方を区別するために掲げられたのぼり旗です。
家中によってその仕様は様々であり、武将によっては複数のデザインののぼり旗を掲げていたとも言われています。
京都のれんでは、実際に存在したと言われているデザインから、各武将の解説のより、存在したのではないか?と思われるデザインまで。様々な「武将のぼり旗」をご用意しております。
【豊臣秀次】
戦国時代から安土桃山時代にかけての武将・大名。
豊臣氏の2代目関白。�豊臣秀吉の姉である瑞竜院日秀の長男。
古筆を愛し、多くの公家とも交流をもつ教養人でもあった。
<基本仕様>
サイズ :180cm×60cm
素材 :ポリエテルポンジー
染色技法:昇華転写
縫製 :四方三巻
チチ位置:左チチ(左5つ上3つ)
1枚ずつPP入れ
武将のぼりは敵味方を区別するために用いられたものです
戦国の争乱を沈めて天下人になったのが豊臣秀吉ですが、この秀吉の姉の長男として生まれたのが豊臣秀次です。
幼少時には戦国大名の浅井長政の家臣、宮部継潤が秀吉の調略に応じる際に人質になってそのまま養子として迎え入れられたなどの歴史を持ちます。
豊臣秀次は戦国時代から安土桃山時代にかけての武将で、家紋は秀吉と同じく五七の桐になります。
家紋は武将のぼりに使われることが多いものですが、武将のぼりは戦場で敵と味方を区別する目的で作り出されたもの、これが現代ののぼり旗の原点といっても過言ではありません。
武将のぼりは目印要素が強いわけですが、これはのぼり旗についても同じで、最近では武将のぼりと呼ばれているのぼり旗に人気が集まっています。
武将のぼりは教養にも役立つものです
豊臣秀次の家紋は五七の桐とよばれているもので、ゴマノハグサ科の樹木であるキリの葉や花を図案化してあるのが特徴です。
家紋はそれぞれの家に存在するものではありますが、のぼり旗に歴史上の人物、例えば豊臣秀次と豊臣秀吉、2つののぼり旗を並べた際に両者が共に同じデザインであることがわかる、これは一種の教養として使うこともできるのではないでしょうか。
家紋を取り入れたデザインはシンプルなものになるメリットがありますが、歴史が好きな人はのぼり旗を見ることでどのような武将の家紋であるのかがわかる、興味ある人にとっても有名な武将の紋は記憶に残りやすいなど、のぼり旗を使った宣伝効果にも期待が高まります。