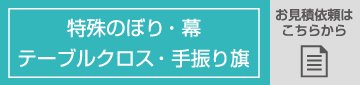真田幸村1
防炎加工
生地変更
―武将のぼりとは―
複数の武士団が入り乱れる戦場で敵見方を区別するために掲げられたのぼり旗です。
家中によってその仕様は様々であり、武将によっては複数のデザインののぼり旗を掲げていたとも言われています。
京都のれんでは、実際に存在したと言われているデザインから、各武将の解説のより、存在したのではないか?と思われるデザインまで。様々な「武将のぼり旗」をご用意しております。
【真田幸村】
安土桃山時代から江戸時代初期にかけての武将、大名。�「真田の赤備え」は有名であり、具足やのぼり旗等あらゆる武具は赤で統一された。
またのぼり旗にある六文銭は、人間・天上・地獄・餓鬼・畜生・修羅の六つの世界を表しており、輪廻天性を繰り返す六道輪廻に由来するものです。
三途の川の渡し賃として六文銭を身につけることで、戦場で死を恐れないという意思表示をしていたと言われています。
<基本仕様>
サイズ :180cm×60cm
素材 :ポリエテルポンジー
染色技法:昇華転写
縫製 :四方三巻
チチ位置:左チチ(左5つ上3つ)
1枚ずつPP入れ
武将の意志を表すのぼりのデザイン
真田幸村ののぼり旗は独特の魅力を持っています。
古来日本では、三途の川の渡し賃が六文だと考えられていました。
旅人はいつ死んでも構わないように、衣服の裾に六文銭を縫い付けていたと言われます。
戦国時代に活躍した足軽なども、そのようにするのが常でした。
そもそも三途の川は三筋の川があるという意味で、渡る方法が3種類あったとされます。
善人は橋を、軽い罪人は浅瀬を、重い罪人は強深瀬を渡りました。
その後渡し船で川を渡るという考え方に変化し、六文銭がなければ衣服を奪い取ると考えられるようになったとのことです。
三途の川の渡し賃は六道銭とも言われますが、その六道とは天道・人間道・修羅道・畜生道・餓鬼道・地獄道で構成される仏教の世界観を指します。
迷いのある者はこの六つの世界を輪廻するという考え方です。
六道にはそれぞれ地蔵菩薩がおり、その地蔵菩薩に一文銭を渡すことから、死者を葬るときに棺の中に6枚の一文銭を入れる風習ができました。
真田幸村はこの六文銭を家紋にし、死を恐れずに命がけで戦うという意思表示を表そうとしたと言われています。
強大な敵や圧倒的不利な状況でも知恵を絞り、知略を重ねて何とか勝ちを得ようとする気概が溢れるのぼり旗です。
見た目に美しいだけではなく、優美で勇ましい印象を受けます。