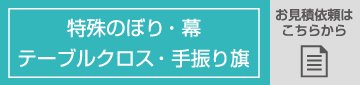柴田勝家1
防炎加工
生地変更
―武将のぼりとは―
複数の武士団が入り乱れる戦場で敵見方を区別するために掲げられたのぼり旗です。
家中によってその仕様は様々であり、武将によっては複数のデザインののぼり旗を掲げていたとも言われています。
京都のれんでは、実際に存在したと言われているデザインから、各武将の解説のより、存在したのではないか?と思われるデザインまで。様々な「武将のぼり旗」をご用意しております。
【柴田勝家】
戦国時代から安土桃山時代にかけての武将・大名である。
若い頃から、織田信長の家臣として仕え織田家の重鎮であった。
<基本仕様>
サイズ :180cm×60cm
素材 :ポリエテルポンジー
染色技法:昇華転写
縫製 :四方三巻
チチ位置:左チチ(左5つ上3つ)
1枚ずつPP入れ
のぼり旗から感じる歴史
のぼり旗とは長方形の布を棒で固定させ、コンビニストアの商品の広告や選挙運動の宣伝などアピールしたい事をプリントして目立つところにかけられて使われています。
しかしその起源は、武家たちの戦のために使われたのが始まりです。
室町時代以降、武家同士が争うようになって合戦が繰り返されます。
俗にいう戦国時代ですが、敵味方が入り乱れる戦場で敵と味方を区別するために、のぼり旗がその目印として活躍したのです。
その証拠に日本では自分たちが劣勢だと「旗色が悪い」と言いますが、それは味方の軍勢が敵に押されていく様が由来となっています。
また「旗を立てる」という言葉はチャレンジする意思を示すのが現在では一般的であるものの、これも戦国時代の合戦の習わしである旗を立てて戦う事を始まるというアピールが由来です。
そんな時代に活躍した偉人は徳川家康や豊臣秀吉など様々いますが、そのうちの1人に数えられる武将に柴田勝家がいます。
幼少の頃の詳細は不明ですが、若い頃から織田家に仕えた彼は当初は織田信長の父である信秀の家臣でした。
信秀が亡くなった後は信長に仕えて重鎮となるものの、本能寺の変をきっかけに力をつけ始めた豊臣秀吉と対立するようになり、越前の北ノ庄城に追い込まれて自害します。
その柴田勝家が用いたのぼり旗は「二つ雁金紋」という家紋が描かれた旗です。
「二つ雁金紋」は渡り鳥の雁をモデルにしており、諸説ありますが縁起を担いでいるとされています。